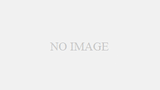こんにちは、「ケアカフェは本日も営業中」へようこそ☕
介護職に就いたばかりのあなたへ。
今回は「介護の現場で新人さんが最初にぶつかりがちな壁」について、一緒に見ていきましょう。
不安や迷いがあって当然!!私もそうでした。でも、それをどう乗り越えていくかで、未来は変わってきます。
ここでは、筆者が経験したよくある壁を8つのテーマに分けて、乗り越え方とあわせて紹介します。
① 利用者さんとうまく話せない…
最初の頃は、「どう声をかけたらいいのか分からない…」と戸惑うことが多いもの。
沈黙になってしまうと「気まずい」と感じてしまうかもしれませんが、実はそんなことはありません。
乗り越え方のヒント
- 無理に会話しなくてもOK。聞き役に徹して、相槌やうなずきだけでも◎
- 天気やテレビの話など、誰にでも当てはまる話題を使って会話のきっかけに
【認知症の方との会話のコツ】
- 過去の職業や趣味について聞いてみる。
- 同じ話を聞かされても「初めて聞く」ような新鮮な反応をするのも◎
- 「そうですね」「大変でしたね」等、共感の言葉を大切に
【会話が続かない時の魔法のフレーズ】
- 「それからどうなったんですか?」
- 「その話、詳しく教えてください」
- 「素敵な話ですね」「すごいですね」

こんにちは、今日もお元気ですか?”って言葉から、ぽつぽつ話が広がることもあるんだよ。大丈夫、ゆっくりでいいんです
② 職場の空気に馴染めない…
スタッフ同士の距離感や雰囲気に、最初は戸惑うこともあるかもしれません。
特に、他職種が関わる現場では距離を感じやすいものです。
乗り越え方のヒント
- 基本的なあいさつを欠かさず、「お疲れさまです」から関係づくり
- 質問したいときは「お忙しいところすみません」と前置きして切り出す
【職場での人間関係構築術】
- 休憩時間には積極的に休憩室に顔を出す。
- 先輩の話を最後まで聞く姿勢を大切に。
- 「ありがとうございます。」を必ず伝える(好感度アップですよ)
- 職場の暗黙のルールや習慣を観察して理解する。
【他職種との上手な付き合い方】
- 看護師:医療的な判断が必要な時は必ず相談
- ケアマネ:利用者さんの生活全体の変化を報告
- 栄養士:食事に関する気づきを積極的に共有

“ありがとう”と“お願いします”この言葉をきちんと伝えると、安心してもらえますよ♪
③ 先輩のスピードについていけない…
先輩の介助はとても早くて丁寧。自分は遅くてミスばかり…。
そんな風に感じてしまうのは、新人さんにありがちなことです。
乗り越え方のヒント:
- 最初はスピードより正確さと丁寧さを大切に
- 先輩の動きを観察し、「どうすれば早くて安全なのか」を学ぶことが大事!
- 身体介護は数をこなすことが、一番上手くなります。失敗も大事な経験ですが、怪我には注意。
【効率アップのテクニック】
- 動線を意識する:無駄な動きを減らし、必要なものは時前を意識する:無駄な動きを減らし、必要なものは事前に準備。
- 両手を使う:排泄介助の際に、ベッド上で横向きが難しい場合。片手で支えながらもう片方の手でパッドやおしり拭きを使用する。
- 予測する力:利用者さんの動きや反応を先読みする。
- 道具の活用:スライディングボードやスライディングマット等の福祉用具を積極的に使用する。
【先輩から技術を学ぶポイント】
- 利用者さんへの声掛けのタイミング
- 移乗の際の手の位置や力の入れ方
- 利用者さんへの気遣いの仕方
- 時間配分の方法
【練習のコツ】
- 休憩時間に同期と一緒に練習し合う。
- 家族や友人に協力してもらって家で練習。
- 鏡を見ながら自分の姿勢をチェック。

筆者も最初は、排泄介助や移乗介助は失敗ばかりしてました。
でも、回数を重ねているうちに、排泄介助や移乗介助のコツが段々と掴める
ようになりました。よく上司に、「先輩の技術を盗んで覚えることも大事」
と教えられたことがあります。それぞれのやり方を見て、自分に合った身体介護
をやっていきましょう。
④ 一人で任されるのが不安…
先輩が別の業務に回り、自分だけで利用者さんを任される瞬間。
とてもプレッシャーを感じる場面ですよね。
乗り越え方のヒント:
- 任される=信頼の証。まずは「できることから」やってみよう
- わからない時・不安な時はすぐに相談。無理は禁物!
【一人で対応する時の心構え】
- 事前に利用者さんの情報をしっかり確認。
- 緊急時や連絡先などの対応方法を把握。
- 「できること」「できないこと」を明確に区別する。
- 無理をせず、早めの相談を心がける。
【緊急時の基本対応】
- 落ち着いて状況を把握する。
- 利用者さんの安全を確保する。
- 直ぐに看護師や上司やスタッフに報告する。
- 必要に応じて救急要請。

“できない”って言える勇気も、すごく大事です。
でも、貴方はひとりじゃないから安心して
⑤ 業務が多すぎて覚えきれない…
記録・掃除・食事・レクリエーション・バイタルチェック…。
新人さんにとっては、どれもこれも新しくて覚えるだけで精一杯。
乗り越え方のヒント:
- 「今日はこれだけ覚えよう」と小さなゴールを設定する
- 優先順位を意識して取り組み、できたことに〇をつけて自信に
【効率的な業務の覚え方】
- 業務を分類する:必須業務・定期業務・臨時業務の3種類に分ける
- 時系列で業務を整理する:マニュアルを見て1日の流れに沿って業務を行い自分だけのメモを作成。
- チェックリストを活用:記録の入力漏れや報告漏れがないよう、マイチェックリストを作ってみる。
- スタッフ職員のマネ:上司や先輩の動きを観察し、真似してみる。
【業務優先順位の考え方】
- 緊急度が高い:利用者の安全に関わること。
- 重要度が高い:必要な記録や報告。
- 定期的なもの:バイタルチェック、清掃など。
- その他:レクレーションなど。
【時間管理の仕方】
- 15分単位でスケジュールを組む。
- 移動時間も計算に入れる。
- 予備時間を必ず確保。
- 「ついで」にできることを見つけてみる。

1日の業務マニュアルに目を通したり、マニュアルを見ながら業務遂行、教わったことをメモしてマニュアルに書き込んでいくと、更に深い自分だけの業務マニュアルが出来上がります。
⑥ 体力的にきつい…
立ち仕事、夜勤、腰への負担。介護職は体を使う仕事なので、体調を崩す人も少なくありません。
介護職も体育会系と思えば・・いいかもしれませんね(笑)
乗り越え方のヒント:
- 正しい介助姿勢を学び、体に負担をかけない工夫を
- 水分・睡眠・栄養のバランスを整える「自分ケア」を忘れずに
体力維持・向上のための対策
【正しい身体の使い方】
- ボディメカニクス:大きな筋肉を使い、小さな筋肉の負担を減らす。
- 腰痛予防:膝を曲げて腰を落とし、物を持ち上げる。
- 足腰強化:階段昇降の軽いストレッチで筋肉をほぐす。
【夜勤対策】
- 仮眠の取り方:20~30分の短縮時間の睡眠で疲労回復。
- 食事管理:夜勤中は、消化の良いものを少量ずつ摂取する。
- 光の調整:夜勤明けの日の光は、体内時計のリズムを崩してしまうので、なるべく日の光に当たらないようにしましょう。
- 休日の過ごし方:休みの前日に夜更かししすぎて、朝起きれないことも・・・。無理に昼夜逆転せずに、体調に合わせて自分の身体を調整しましょう。
【栄養・水分補給】
- こまめな水分摂取(1日2ℓを目安に)
- たんぱく質を意識した食事を摂取する。
- ビタミンB群で疲労回復
- 休憩時間の栄養補給を忘れずに。
【疲労回復法】
- 入浴で血行促進。
- 質の良い睡眠(7~8時間が目安)
- 適度な運動習慣
- マッサージや生体の活用

介護職は体を使う仕事なので、どうしても疲れが取れません。
その時は、無理をしないでリフレッシュ休暇を取って、身体を休ませる
ことがいちばんです。
⑦ 職場の輪に入れない…
スタッフの輪にうまく入れず、孤独を感じてしまうことも。
でも、少しずつ関係を作っていければ大丈夫です。
乗り越え方のヒント:
- 挨拶+ひとこと会話(「お疲れ様です」「こんにちは」など)からスタート
- 休憩中の雑談などで、少しずつ“つながり”を増やしていこう
【積極的なコミュニケーション(筆者が実際に行ったこと)】
- 共通の話題:利用者さんの話、好きなこと・嫌いなことの情報を聞いてみる。
- 感謝の気持ち:小さなことでも「ありがとうございます。」と伝える。これだけでも好感度が高くなります。
- 相談する:分からない事を素直に聞く姿勢。分からないまま時間が過ぎていくと、信頼関係が少しずつ崩れていくので注意ですよ。
- 手伝いの申し出:利用者さんの対応で業務進まないスタッフに「何か手伝うことは、ありますか?」と聞いてみる。
【信頼関係の構築方法】
- 約束を守る(時間・書類提出の締め切りなど)
- 秘密を守る(利用者情報・同僚の相談など)
- 一生懸命さを見せる
- 失敗を素直に認め、改善する姿勢

挨拶からスタートしていけば、自然と会話が増えていくんですよ。
分からないことがあれば、直ぐに聞くこと。モヤモヤした状態で
仕事をすると必ずミスは起こります。素直に聞く姿勢を見せることが大事です。
⑧ 専門知識についていけない…
ケアプラン、記録、アセスメントなど、専門的な内容も徐々に出てきます。
最初は「難しすぎて理解できない」と感じるかもしれません。
乗り越え方のヒント:
- 先輩の記録や言い回しを真似しながら、少しずつなじんでいく
- ノートやメモ帳を活用して、自分なりに情報をまとめる習慣を
専門知識習得の効率的な方法
【基礎知識の体系的学習】
- 介護保険制度:サービスの種類と利用方法
- 認知症ケア:症状の理解と対応方法
- 身体機能:加齢による変化と疾患の基礎知識
- 感染症対策:標準予防策と適切な手洗い・消毒
【実践的なスキルアップ】
- 記録の書き方:SOAP記録法などの基本フォーマット
S:主観的データ
O:客観的データ
A:評価
P:計画 - 観察力の向上:利用者の変化を見抜く目を養う。
- コミュニケーションの技術:傾聴とアサーション
アサーション:「自己主張」ですが自分も相手も大事にして主張はしっかり行うも、相手を傷つけない絶妙なコミュニケーションです。 - 緊急時対応:応急手当と緊急連絡の手段
【継続学習の工夫】
- 研修参加:職場内外の研修に積極的に参加
- 資格取得:実務者研修・介護福祉士などの資格取得を目指す
- 読書週間:専門書籍や業界誌の定期購読
- 情報共有:同僚との知識や経験の共有

介護職では専門用語がいっぱい出てきます。
もちろん私も。専門用語を覚えるのに苦労しましたが、専門書籍や先輩からの教えで少しずつ専門用語を覚えることが出来ました。
こひなちゃんの“壁乗り越えチェック”

| 壁 | ひとこと アドバイス | 実践ポイント |
| ①利用者さんと話せない | 聞き役になってみよう | 過去の話を聞き出す |
| ②職員とうまく話せない | 挨拶+笑顔の積み重ね | 他職種との連携を意識する |
| ③先輩の速さについていけない | 丁寧+観察がコツだよ! | 効率化のテクニックを学ぶ |
| ④一人に責任が重い | 「任される=信頼」 | 緊急時対応を準備 |
| ⑤業務が多すぎる | 今日はこの業務を覚えよう | 優先順位と時間管理 |
| ⑥体力が持たない | 利用者もだけど、 自分のケアも忘れずに | 正しい身体の使い方 |
| ⑦輪に入れない | 挨拶から信頼関係が生まれる | 積極的な参加姿勢 |
| ⑧専門知識が追い付かない | 他の人をマネしながら覚える | 体系的な学習計画 |
おわりに
いかがでしたでしょうか?
どんな仕事にも「新人時代の壁」があります。
でも、その壁は、あなたが成長しようとしている証拠。
焦らず、少しずつ、自分のペースで乗り越えていきましょう。
ケアカフェでは、これからもあなたの“がんばる気持ち”にそっと寄り添っていきます。
またのご来店をお待ちしています☕✨